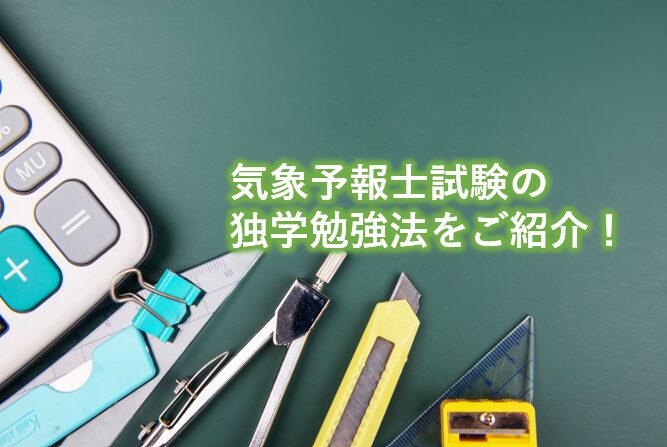【5分で読める!】気象予報士実技試験は過去問が最強!合格するための効率勉強法を徹底解説!
皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。
これから初めて気象予報士試験を受けてみようと考えている方や、学科は一部受かってる方などの中には、次の試験に向けて、どんなことをすればよいかよくわからない方もおられるのではないでしょうか。
私は自分が気象予報士になるまで(なってからもですが。)、気象予報士の方や気象予報士を勉強している方にも会ったことがありませんでした。
そのため、試験に向けてどのように勉強すればよいかもよくわからず試行錯誤しており、独学で勉強する方に向けて何か指針となるものがあればな・・と常々思っていたんですね。
そこで私自身の経験も踏まえ、個人的によいと思う勉強方法について試験までの月別カウントダウン形式でご紹介していきます。
独学での勉強方法に不安の方はぜひ確認してみてください。
気象予報士試験に向けて
6カ月前にやっておくこと
ここでは試験6カ月前にやることについてご紹介します。
試験6カ月前というと、ちょうど前の試験が終わったすぐあとくらいなりますね。
次の試験に向けての作戦を練っていく時期になります。
①初めて受験する方
次の試験で初めて受験する方にとっては、さて何から手をつければよいかと考えている方も多いのではないでしょうか。
気象予報士試験は一般知識、専門知識、実技試験とすべての試験をクリアする必要がありますが、最初の試験でこの3つをすべてクリアするのはかなりハードルが高いです。
私のおすすめとしては、まず学科試験である一般知識or専門知識をまずどちらか合格するということを目標に設定することがよいと考えます。
というのも、別記事でも紹介しておりますが、学科試験は1年間の免除があるため、どちらか合格すれば、次に合格しなければいけない科目への勉強時間の比率を上げ、それに注力することができるからです。
また学科試験をクリアしていないと実技試験は採点すらされませんので、中途半端に実技含めすべての科目を勉強していたとしても学科が合格していなければ、せっかくの勉強時間が無駄になってしまう可能性もあります。
気象予報士試験ってどんな試験?試験内容や合格基準についても解説!
1回目の試験で一般知識or専門知識、2回目の試験で一般知識or専門知識、3回目の試験で実技試験という流れで合格していけば、効率よく最短合格を目指せます。
②学科一部、または学科全て合格されている方
試験が終わったばかりで次のことを考える余裕もない方もおられるのではないでしょうか。
結果がでるのは試験が終わった約40日後なので結構時間がありますよね。
結果がでてから勉強にとりかかろうと思う方はそれはやり方の1つなのでそれでよいです。
ただ自己採点で結果が良くなかった方は次に何を受験する必要があるかは考えておくべきです。
学科一部合格の方は、その学科の免除がいつまであるかを確認しましょう。
まだあと1年後まであるというかたは、次の試験では残りの学科を合格することを目標にするのがよいです。
学科一部と実技合格を狙うより実技のみを狙うほうが傾向として合格率が高くなっています。
学科は確実に合格するつもりで勉強計画を立てていくことをおすすめします。
学科をすべて合格されている方は、残り実技のみになりますので、ここが山場になります。
次の試験で実技を落としてしまうと、学科が復活してしまい、次の試験に対するモチベーションが下がりずるずると試験回数も増えていってしまうので、次の試験で確実に実技をクリアし完全合格を勝ち取りましょう。
5~2カ月前にやっておくこと
ここでは勉強の核となる期間であろう時期にやっておくことについて紹介します。
①初めて受験する方
受験する科目が決まれば早速それに向けて勉強を進めていくことになります。
参考書は何がよいのか本屋に向かう方もおられるのではないでしょうか。
そこで、私が参考書としておすすめする教材について以下にご紹介します。
一般知識、専門知識に共通しますが、らくらく突破シリーズ、イラスト図解よくわかる気象学のテキストは初心者や文系出身の方でもわかりやすく解説してもらっているテキストになり初めてでも読みやすい教材です。
バックグラウンドに理系の知識がある方などは一般気象学を読んでみて理解を深めていくことをおすすめします。
ただ文系の方は難しいと思いますのでらくらく突破シリーズ、イラスト図解よくわかる気象学を隅々まで理解してインプット・アウトプットができるようになれば十分です。
また専門知識では気象予測などの考え方も定期的に変わってくるため、日頃から気象庁のHPの知識・解説などを確認しておくことも重要です。
最初の2カ月程度で教材を読み込み理解して、残りの月で過去問に取り掛かりましょう。
学科の過去問は、約10年間程度さかのぼって問題を繰り返しといていくのがよいです。
また答えを覚えて解いていくだけではなくなぜそのような解答になっているかもよく考えながら類似の問題がでたときに即答できるようにしておくことがとても大切です。
一般知識
・らくらく突破気象予報士かんたん合格テキスト(一般知識編)
・一般気象学
・気象予報士試験精選問題集
・過去問
↓精選問題集は学科、実技ともに勉強することが可能です。
専門知識
・イラスト図解よくわかる気象学(専門知識編)
・気象庁HP→気象庁|知識・解説
・気象予報士試験精選問題集
・過去問
②学科一部、または学科全て合格されている方
前回試験の結果が発表され学科一部合格していて、次で学科一部と実技合格としないといけない方もでてきているかもしれませんね。
その方は学科3、実技7の割合くらいで勉強していくようにしましょう。
学科については初めて受験される方よりも知識はあるはずですので、参考書はさらっとみる程度で過去問を重点的に解いていくことをおすすめします。
残りの科目が実技のみとなった方は、らくらく突破シリーズで理解を深めていき、残りは過去問を繰り返しといていきましょう。
目安としては過去7.8年間分を解いていくのがよいでしょう。
あまり古い問題では現在の問題の出題の傾向と変わっている部分や、合格率を一定にしておく観点から年々難化傾向にありますのでこれくらいの年数でしっかり問題をといていくことがベストです。
7年といっても1年に2回ありさらに2題ずつ出題されるので28回分の問題をといていくことになりますので、かなりのボリュームです。
こちらも学科試験同様、なぜそのような答えになっているのか自分の考でよいので理屈をつけて解答できるようにしましょう。
もし間違っていれば考え方を都度修正していけばよいので。
あと実技試験は学科試験とは異なり、筆記試験となります。
自分で時間を計測してやってみるとわかると思いますが、最初のうちは全然時間が足りません。
でも大丈夫。それが普通なので。
なぜそのような答えになっているのかというのを考えるのがとても大切で、理解を深めていくと一つ一つの問題を解くスピードも上がってきます。
もう一度言いますが、ただの暗記ではなく理解するということを意識して解くようにしていってみてください。
実技試験
・らくらく突破気象予報士かんたん合格テキスト(実技編)
・気象予報士試験精選問題集
・過去問
1カ月前から前日
試験1カ月前からの勉強方法について紹介していきます。
①初めて受験する方
このころになると学科の知識もだいぶ定着してきているのではないでしょうか。
ただこの期間をさぼってしまうと、今までの知識が無駄になってしまいますので、毎日10分でも勉強を続ける習慣をつけていく方がよいです。
人間は、次の日には前日の3割程度しか記憶が残っていないので、定着させるためには毎日少しの時間でも勉強を続けることが大切です。
ちなみに私の場合は電車での通勤時間を利用して日々の勉強時間を確保していました。
勉強ツールについては引き続き過去問を重点的に解いていきましょう。
繰り返し問題をといているとよく間違える問題なども見えてくるころかと思います。
すでに理解している問題よりは、そういった問題にチェックをいれて繰り返し解いて理解していくようにしましょう。
②学科一部、または学科全て合格されている方
次で学科一部と実技を合格しないといけない方にとっては、大丈夫かなと不安になってくる時期です。
この時期ではもう一度学科の知識を復習しておくことが大切です。
次の試験で学科が合格しなければ、実技は採点されません。
ですので、学科の過去問においてはどれが出題されても大丈夫というくらいのレベルまで自分の実力を上げておくようにしておきましょう。
実技試験のみを勉強している方は過去問の理解も深まって、少しずつ問題を解くスピードも上がってきているのではないでしょうか。
気づいてきているころかとは思いますが、実技試験は学科の勉強の上に成り立っています。
そのため、学科の知識が少なければ解けない問題も多く、実技の問題を見て、わからなければ学科の参考書を見て理解して、といったことも増えてきているはずです。
勉強の仕方はそれで全く問題ありません。
わからないところをわからないまま放置するのは一番よくないので、時間がかかってもそのやり方は崩さない方がよいです。
特に前線解析など作図問題に苦戦される方も多いはずです。
なぜそのような作図になるのか答えと天気図をよく見比べながら、自分の考えを整理していくようにしてみてください。
それともう一つ重要なこととして、実技は筆記試験です。
筆記試験ということは人が採点しています。
記述の模範解答はありますが、一字一句それと同じにならないといけないわけではありません。
人によって解釈幅もありますので、特定のキーワードが入っていたり、作図問題で多少ずれていたとしても、根拠をもって記載していることが伝われば正解もしくは部分点をもらえる可能性もあります。
採点者は解答からしかその人がきちんと理解して記載しているかを把握することができません。
逆に理解して書いているんだぞ。ということを採点者にわかるよう記載できれば正解や部分点につながる可能性は大いにあります。
採点者のことも想像しながら解答を作成することも一つのポイントになります。
試験当日
いよいよ試験当日ですね。
ここまで勉強おつかれさまでした。体調はよいでしょうか。
今までの努力は決して無駄ではありません。
後悔のないよう自分を信じて頑張ってきてください!
①初めて受験する方
初めて受験される方にとっては緊張もありそわそわしていることでしょう。
でも初めての人はみんな同じ気持ちなので大丈夫ですよ。
いままでやってきたことを信じるのみです。
学科試験は60分です。15問出題されますので、一問あたり4分程度で解けばよい計算になります。
ざっと一通り目を通して解けそうな問題から解いていくのも一つの方法です。
時間は十分あると思いますが、学科試験ではひっかけの問題や自分がこれだと思って解答をしても全く異なる解答になっている場合もあります。
問題はきちんと読んで、意図に即した解答になっているか全問見直しをするようにしましょう。
学科試験のみを勉強した方にとっては、午前中の試験が終わると退席していく方が多いです。
ただ、初めての方でも昼の実技試験は受けておくことをおすすめします。
実技試験の雰囲気を味わっているのとそうでないのとで、次の試験に向けて一歩先にでることができます。
また問題も持って帰れるのであとで復習したりできるのはメリットかと思いますので、是非受験してみるようにしてみてください。
②学科一部、または学科全て合格されている方
学科一部と実技の方にとっては最初の山場である学科試験になります。
学科は確実に正解できている問題を積み上げていきましょう。
11問以上正解すれば合格になるので、確実に取れる問題はおとさないようにすることが必要です。
気象予報士試験ってどんな試験?試験内容や合格基準についても解説!
午後からは実技試験になり、75分×2の長丁場となります。
1つ終わっただけでも結構疲れるのでインターバルでの飲み物やお菓子など、自分の実力を最大に発揮できる携行品の準備も大切です。
実技試験は75分ですが、初めて見る問題も出題される可能性があり、1つにかける時間も限られていいます。
最初に登場する問一の穴埋めなどは5分程度でやりきって、ほかの問題にかけれる時間を少しでも増やしていくことがポイントです。
それとなんども言いますが、問題は本当によく読みましょう。
例えば、送り仮名を間違えてミス、整数値のところ小数点で記載してミス、8方位のところ16方位で記載してミス、風の変化を問われているのに気温の変化を解答してミスなど、基本的なところでの間違いは極力へらしましょう。
このようなところで間違えていては合格ラインには届かないと思っておいた方がよいです。
合格する人は基本的な問題は間違いません。初めて見る問題や難しい問題はほかの人もわからないことが多いので、差がでるのは基本的な問題の正答率です。
問題をよく読んで問われていることに沿った答えを記載するようにしましょう。
あたりまえのことですが、これがなかなかできていない方も多いので、このあたりは頭の片隅にいれて問題を解くようにしてみてください。
【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!
まとめ
6カ月前からの独学での勉強方法について、個人的な思いも含めて記載してきました。
自分に合いそうだなと思えば参考にしていただければと思いますし、そうでなければ自分にあっているやり方を考えてみてもらってもよいです。
本記事にも登場するワードですが、暗記と理解は異なります。
自分の覚えたことをだれかに説明できるくらいになっていれば理解度が十分についているはずです。
気象予報士試験では全く同じ問題はほぼ出題されませんので、問題をよく読んでいかに自分の記憶をたよりに適切にアウトプットできるかが、重要です。
過去問の知識が十分であれば、この問題はこの天気図をみてこんな感じで解答するんだなということが一瞬ででてくるようになります。
それくらいのレベルになれば十分合格も可能だと思いますので、是非自分の実力を高めて合格を勝ち取とってくださいね。
【テンプレ暗記用】気象予報士実技試験の記述解答を全部丸暗記帳!(過去10年分以上)
最後までお読みいただきありがとうございます!