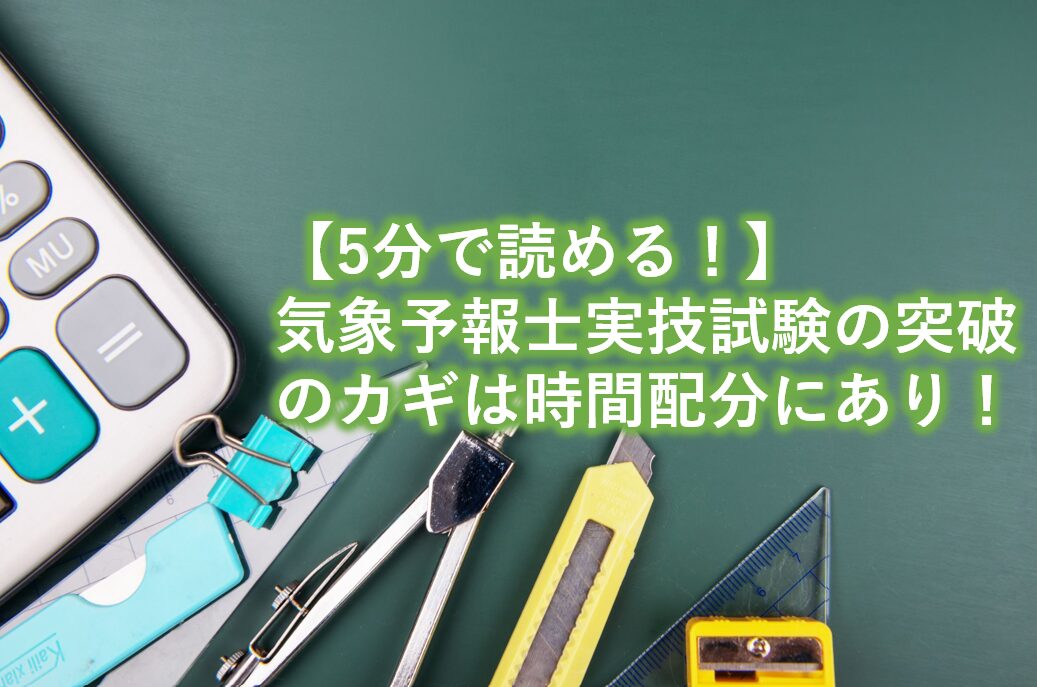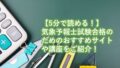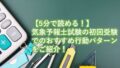皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。
学科試験に合格したことはあるけど、実技試験がなかなかうまくいかない、何度受けても最後まで解答を埋めることができないと悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
「実技の壁」ともいわれる気象予報士試験。
これをどのように乗り越えていくかを考えることも完全合格のポイントになります。
実技試験を突破できる実力があっても、上手な解答方法を知らないと、合格ラインに到達しない場合もあるんですね。
今回の記事では実技試験突破のカギとなる時間配分の考え方についてご紹介していきます。
試験前には”ちょっと、だれか先に教えといてよ!”と思った個人的に知っておきたかった情報ですので、気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
実技試験は時間配分が命
気象予報士試験の実技試験では、実技1.2と75分の問題が2回行われます。
学科試験と違う点は記述試験であることと、時間の長さになります。
一般知識や専門知識などの学科試験はそれぞれ60分ですので、それに比べると時間があるように思うかたもおられるかもしれません。
でも実際やってみるとわかりますが、全く時間が足りないんですね。
きちんと勉強して臨んだ人ですら、時間が足りないので、初めて受験される方であれば、完答できる方はかなり少ないのではないでしょうか。
では、どうすれば完答できるようになるのか。
もちろん実技試験の知識はしっかりと身につけたうえでですが、特に考えておく必要があるのが試験を解くための時間配分です。
気象予報士試験に関わらず、資格試験は当然ながら制限時間というのが決められていますよね。
問題数に対して十分時間がある試験では、考える必要はほとんどありませんが、この気象予報士試験では考えておかないと確実に足元をすくわれます。
これから解説していく秘訣は、時間短縮できるところは最大限短縮し、逆に時間をかける必要がある問題に時間をかけ、自分のもってる実力を後悔することなく発揮するためのコツをまとめたものです。
試験終わった後に「あーあれやっとけば・・。」と思われたことがある方も多いのではないでしょうか。
試験前に知っておくだけでも、時間管理がしやすくなり、解答時間短縮につながるはず。
では、早速、これを読まれている皆さんにだけ、実技試験突破に向けた10個の大切な秘訣をご紹介していきますね。
どの参考書にも書いてないので必見です。
時間配分の秘訣①
時間配分の秘訣①は「スタートダッシュは肝心」です。
時間制限がある試験でかつ、問題量が多い場合、解答を考える時間をどこで捻出していくかが重要になります。
その1つがスタートです。
実技試験では、スタートと同時に問題用紙を開くのですが、天気図が切り離し可能となっています。
【5分で読める!】気象予報士試験での問題は破る?気象予報士がわかりやすく解説!
これを破るか破らないかでまず1.2分は変わってくるんですね。
もし、時間を優先するのであれば、周りの人は気にせず、破らないまま問題にすぐさま取り掛かってください。