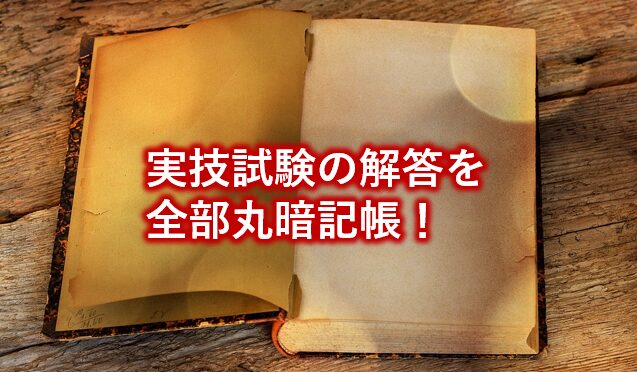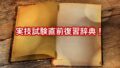【5分で読める!】気象予報士実技試験は過去問が最強!合格するための効率勉強法を徹底解説!
皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。
実技試験での解答を記述するときに、うまく解答字数におさまらない、どのように書いたらいいのかがすぐ思いつかない、といった悩みを持たれているかたも多いのではないでしょうか。
一般的に、記述の解答をするときは解答字数に対して±5字以内程度に収めることがよいとされています。
ただ、そもそも問題に対しての解答のキーワードが思い浮かばなかったり、気象用語を用いた独特の言い回しなどがぱっと思いつかなければ解答を書くこともできませんよね。
そこでおすすめなのが、記述の解答を丸暗記するというものです。
もちろん、実技試験を2~3周は理解して解いた上で使用するということはご理解くださいね。
このブログを読んでいただいている方なら、「えっ、暗記より理解する方が大事なんじゃないの?」と思われる方もおられると思います。
はい、そのとおりです。
ただ、実技試験をやってみるとわかりますが、時間が圧倒的に足りないんですよね。
時間のない中で解答をすばやく作成するためには自分がどれだけ、気象用語や解答表現方法をインプットをしているかということも大切になってきます。
実際に私も行っていた方法ですが、やり方として、実技試験の問題を理解しながら時間をかけて何度か解いたあと、記述の解答だけを眺めて丸暗記するというのがおすすめです。
そうすると、解答を見ただけで、この問題のときには、この解答だったなというのがすぐ思いつくようになります。
それが、できれば上出来です。
気象予報士試験ではイレギュラーな場合もありますが、ある程度、問題のパターンがきまっていることが多いです。
なので、解答を覚えておくと、「この問題のときにはこの表現とこのキーワードを記載すればいいんだな」というのが瞬時に思いつくようになり、その記憶をたよりに記載すれば字数も概ね解答字数に近づけることができるというわけです。
アクティブリコールも組合せた記憶力アップの勉強法。
私も試験時間最後の1.2分で解答の表現方法を覚えていたおかげて記載することができた経験もありますのでだまされたと思ってぜび、やってみてください。
実際の試験で覚えたことが、かならず役にたつはずです。
今回、過去問の記述解答例を以下に記載しております。実技試験の記述対策としてぜひご活用いただればありがたいです。
【5分で読める!】気象予報士実技試験の突破のカギは時間配分にあり!完全完答のコツをご紹介!
- 実技試験の記述解答を全部丸暗記帳
- 第65回 気象予報士試験 実技1
- 第65回 気象予報士試験 実技2
- 第64回 気象予報士試験 実技1
- 第64回 気象予報士試験 実技2
- 第63回 気象予報士試験 実技1
- 第63回 気象予報士試験 実技2
- 第62回 気象予報士試験 実技1
- 第62回 気象予報士試験 実技2
- 第61回 気象予報士試験 実技1
- 第61回 気象予報士試験 実技2
- 第60回 気象予報士試験 実技1
- 第60回 気象予報士試験 実技2
- 第59回 気象予報士試験 実技1
- 第59回 気象予報士試験 実技2
- 第58回 気象予報士試験 実技1
- 第58回 気象予報士試験 実技2
- 第57回 気象予報士試験 実技1
- 第57回 気象予報士試験 実技2
- 第56回 気象予報士試験 実技1
- 第56回 気象予報士試験 実技2
- 第55回 気象予報士試験 実技1
- 第55回 気象予報士試験 実技2
- 第54回 気象予報士試験 実技1
- 第54回 気象予報士試験 実技2
- 第53回 気象予報士試験 実技1
- 第53回 気象予報士試験 実技2
- まとめ
実技試験の記述解答を全部丸暗記帳
第65回 気象予報士試験 実技1
- どちらも台風の眼が見えるが、9時の眼の方が小さく明瞭である(壁雲が発達している)
- 9時には台風の中心を囲んでほぼ円形に密集して分布しているが、21時にはらせん状で隙間がある。
- ほぼ全域で上昇流となっており、中心付近(中心のすぐ北西側)に-93hPa/hの極値がある。
- ほぼ全域で湿数3℃以下となっている。
- 中心付近が周辺より高温となっている。
- 対流雲域付近は全層で上昇流となっているが、北緯40°付近は700(750)hPa付近から上空で下降流となっている。
- 山脈の風下側は概ね下降流、風上側は概ね上昇流で、風下側は風上側より気温が高い。
- 中心の南~西側が下降流となり、南側が相対的に乾燥する。
- 中心の西~北側が相対的に低温となる。
- 風向が反時計回りに変化したため。
- 台風が鳥取県の東側を通過し、北よりの強い風による地形の影響によって台風に伴う降水が強まったため。
第65回 気象予報士試験 実技2
- 渡島半島付近の低気圧に伴う雲域と比べ、中心付近の雲頂高度は低く、雲頂高度の高い雲は中心から離れた北側に分布しており、バルジはみられない。
- 中心の北側で強い上昇流域、南西側で強い下降流域となっている。
- 気温が0.5℃以下で、10分間降水量が0.5mm以上である。
- 降水開始とともに17時30分まで小さくなり、その後はほぼ一定で、20時10分以降急速に大きくなり、降水は終了した。
- 前線面付近の1.2kmで北東風(1.5kmで東南東風)、5kmでは強い南西風で、風が上方に向かって時計回りに変化している。
- 16時40分には0.9kmであるが、その後は次第に上昇し21時(20時40分)には2kmに達している。
- Bのほうが湿潤域との対応が良く、南西風が上空に向かって強まる領域に対応している。
第64回 気象予報士試験 実技1
- 台風の北にある雲域の北縁に見られるCiストリーク(細長い筋状の上層雲)があるため。
- 発達した対流雲域は中心付近から東側に偏り、その他の領域にはほぼない。
- 上昇流の極大点は中心付近ではなく北東側にあり、南西~北西側は主に下降流となっている。
- 高温域は中心付近ではなく東側にあり、西~北側には低温域が見られる。
- 気層の気温減率が、乾燥断熱減率より小さく、湿潤断熱減率より大きいため。
- 閉塞前線の北側で気圧傾度が急になり、地上低気圧の中心の北東側に強風の範囲が広がる。
- シアーラインに沿ってその西側に降水強度20mm/h以上のエコーが分布している。
- シアーラインの東側は東よりの風、西側は北よりの風で、シアーライン付近で風が収束している。
- シアーラインの東側は西側に比べて気温が高く、シアーライン付近で温度傾度が大きい。
- シアーライン通過後の北よりの非常に強い風(暴風)。
第64回 気象予報士試験 実技2
- 負の渦度移流が見られるところ。
- 気温の安定層の上端であるため。
- 湿数は、前線面から920hPaまでは小さく、それより下層は高度が低いほど大きい。
- 露点温度がほぼ最大となり(気温の上昇は一旦とまり)、風向が南東から南に変わったため。
- 風向が南から南西へ変化し、気温、露点温度の低下が始まった。
- 西南西(南西)の35~40ノットの強い風が領域の南側から吹いており、暖気移流となっている。
- 850hPaの12℃~15℃で南北の温度傾度が大きく、強い南風による暖気移流が強く、700hPaの上昇流が大きいため。
- トラフは、低気圧中心の北から北東に離れていく。
- トラフAは主に12日21時までの発達に寄与し、トラフBはその後の発達に寄与する。
第63回 気象予報士試験 実技1
- 両地点の風速は同じだが、地点Bの方が風向に沿った水平温度傾度が大きいため。
- トラフは東北東進し、西側から地上低気圧に接近する。
- 500hPa面の正渦度域の南縁(渦度ゼロの等値線) に最も近いため。
- 地上低気圧の中心の南東側では、水平温度傾度が大きく相対的な高温域となる。
- 地上低気圧の中心の東側で暖気移流となり、南側で寒気移流となる。
- 地上低気圧の中心付近から東側にかけて最大-80hPa/h の上昇流となり、南側では+20hPa/hの下降流となる。
- 陸上のエコー域付近は、相対的な高圧部となっている。
- 陸上のエコー域付近は、相対的な高温域となっている。
- エコー域が到達すると急下降し、しばらく低い状態が続いた後に上昇した。
- エコー域が到達すると急上昇したが、その後は下降しほぼ上昇前の値に戻った。
第63回 気象予報士試験 実技2
- 気温の安定層の上端であるため。
- 前線面の高度は館野で850hPaより高く、その高度は南側が低いため。
- 上昇流の中心は、地上の台風中心から北東方向に離れていく。
- 伊良湖の風向が時計回りに変化したため。
- 台風の中心位置は直線A上に推定される。
- 台風中心は伊良湖に近づいたが、衰弱し中心気圧の上昇が大きかったため。
- 関東地方北部(および長野県中部)に、寒気が流入する。
- 中心付近の強雨域は急速に弱まるが、中心から離れた御前崎の南東の帯状の強雨域は北東進し強まっていく。
- 台風中心が南西から最接近するまで、南東や東から湿った強い風が吹き、地形の影響で降水が多くなるため。
第62回 気象予報士試験 実技1
- 低気圧の中心の東側は暖気移流、西側は寒気移流で、東側の方が強い。
- 低気圧の中心の東側は最大-56hPa/hの上昇流、西側は最大+17hPa/hの下降流となっている。
- トラフは前12時間とほぼ同じ速度で東進し、西から地上低気圧に近づく。
- トラフは前12時間と比べ東北東に変わり速度を速めて、地上低気圧に追いつく。
- 中部山岳南側の南向き斜面で、南よりの下層風が流入している。
- エコー域の北西側は南東側に比べて気温が低く、エコー域付近で温度傾度が大きくなっている。
- エコー域の南東側は南又は東南東の風、北西側は北北西の風又は相対的に弱い風で、エコー付近で風が収束している。
- 13日3時の方が温度風が強いため。
- 山頂から見て風上側の斜面を中心に上昇流が分布する。
- 相当温位が上方に向かって低くなっている。
第62回 気象予報士試験 実技2
- 地上低気圧の西方に位置する500hPaのトラフが、地上低気圧にさらに近づく予想のため、発達が続く。
- 逆転層の上端であるため。
- 前線面より下層では上方に向かって反時計回りに変化し、前線面より上層ではほぼ南西である。
- 800hPaより上の層で湿数が大きい。
- 鉛直方向の変化が小さい。
- 地上付近を除き絶対安定である。
- 1000hPaから800hPaで条件付き不安定である。
- 西側は北西の風が強く、東側は北の風が相対的に弱い。
- 渦が西郷に最接近する前に西風成分が強まったため、渦は北西側と判断されるため。
- 強い西風の場の中で渦が北側から接近し、南風成分が次第に強まったため、反時計回りになった。
- 渦Bの通過時に、西風成分に負の時間帯がみられるため。
- 気圧は最接近時付近で極小になった。
- 10分間降水量は最接近時の直後に、極大になった。
- 気温は相対的に変化は小さい。
第61回 気象予報士試験 実技1
- 雲域付近では、北東の風と東南東の風が収束し、上昇流となっている。
- 東京上空では、気温が0℃以上の層が薄く、かつ乾燥している。
- トラフAは、深まりながら南東進し、低気圧の西側から低気圧に接近する。
- 低気圧の東側で暖気移流、西側で寒気移流が予想され、低気圧の東側では最大で-41hPa/hの上昇流が予想されている。
- 風向が東から北よりに反時計回りに変化したため。
- 風向が上空に向かって、反時計回りに変化しているため。
- 低気圧西側の下降流によって乾燥した空気が、八丈島付近の高度約2.5km以上の上空まで達したため。
- シアーラインの北西側は、南東側と比較して相対的に低温となっている。
- 気温が0℃前後で大雪となっているため。
第61回 気象予報士試験 実技2
- 等圧線が混んでおり、相対的に南西風が強い。
- 気圧の尾根に位置して気圧傾度は小さく、風が弱い。
- 東北東にのびる高相当温位域の先端付近で風が収束している。
- 雲頂高度はやや高いが、降水はほとんどない。
- 雲頂高度は低いが、強い降水が分布している。
- 雲は団塊状で雲頂高度は高く、雲域は狭い範囲に、非常に強い降水域が線状にのびる。
- 全般に西南西の風で、700hPa付近で50ノットと最も強くなっている。
- 強雨域の南側は50ノットの南西風、北側は相対的に弱い南西風で、その間に収束がみられる。
- 強雨域は、950hPaの集中帯の南端付近に位置する。
- 大雨の前は南南西の風が強まったが、その後風向が時計回りに変化し西になり弱まった。
第60回 気象予報士試験 実技1
- 風向が西南西から西北西に時計回りに変化したため。
- 2つの低気圧は、はじめの12時間はトラフbの進行方向前面で発達し、その後の12時間はトラフaの進行方向前面で発達する。
- 700hpa,地上の気圧の谷に沿って帯状の上昇流域となる。
- 850hpa.地上の気圧の谷に沿って温度場の尾根となる。
- 地上の気圧の谷の北東側は北よりの風、南西側は西よりの風で相対的に強く、気圧の谷付近で風が収束する。
- シアーラインの北西側は相対的に高温、南東側は低温である。
- シアーラインに沿って降水強度5mm/h以上のエコーが分布している。
- 風向が北西から南寄りに変化し、気温が下降、降雪が強まったあとも風は南寄りで気温が低く強めの降雪が続いた。
第60回 気象予報士試験 実技2
- 台風中心と南西側は雲頂高度の低い対流雲、北東側は雲頂高度の高い発達した対流雲が多く分布している。
- 台風中心付近に気温の極大があり、その周辺はほぼ一様である。
- 中心の北西側に乾燥域、北東側と南西側に湿潤域が広がる。
- 台風中心からみて南西側は乾燥域が広がり北東側は全体が湿潤域となる。
- 楕円形から円に近い形に変化している。
- 中心付近に暖気の極大があり、そこからの温度傾度は穏やかである。
- メソモデルでは台風中心の東側に強い降水域が南北方向に帯状に伸びている。
- 雲頂高度の高い対流雲が中心のやや東側にまとまった。
- 粟国は反時計回りの変化で経路の左側、久米島と名護は時計回りの変化で経路の右側と推定されるため。
- 名護は久米島より最低気圧が低く、台風中心がより近くを通過したと推定されるため。
第59回 気象予報士試験 実技1
- -64hpa/hの強い上昇流が解析されており、波動の東側で暖気移流、西側で寒気移流となっている。
- 湿潤層は転移層から上層にかけて分布している。
- 東シナ海から前線面を滑昇した空気中の水蒸気が凝結したため。
- 風向が南から南南西に変化し、気温が1℃上昇した。
- 風向が南西から西に変化し、気温が4℃下降、気圧が1hpa上昇した。
- シアーラインの東側は東南東のやや強い風、西側は北西の相対的に弱い風でシアーライン付近で収束している。
- シアーラインの東側は相対的に高温、西側は低温でシアーライン付近では温度傾度が大きくなっている。
- シアーラインに沿って帯状に20mm/h以上の強い降水エコーが分布している。
第59回 気象予報士試験 実技2
- 中国大陸からの高気圧の張り出しにより等圧線の間隔が狭まり風が強まるため。
- 気温減率の小さい層の上端で風が南から南西に順転している層の上端付近のため。(温暖前線面)
- 850hpa付近で上昇流が最大となり、700hpa付近で弱い下降流となる。
- 北側では上方に向かって風向が西北西から西南西と反時計回りに変化しており寒気移流がある。
- 気温減率が湿潤断熱減率より小さいため。(安定)
- 山bより標高の高い山aの西側では降水量が多く、山aより東側は降水量が少ない。
- 山cのすぐ西側から山頂付近にかけて降水量が多いが山cより高い山dにかけても弱い降水がある。
第58回 気象予報士試験 実技1
- 低気圧中心はトラフaの東300kmにある。
- 低気圧中心の東側は−140hpa/hの強い上昇流を伴う暖気移流の場、西側は+38hpa/hの下降流を伴う寒気移流の場になっている。
- 低気圧中心の北東側には背の高い発達した雲域が広がり南西側は下層雲のみとなっている。
- 低気圧はトラフaと同位置、トラフbの東800kmにある。
- はじめの12時間はトラフaの進行方向前面で発達し、その後の12時間はトラフbの進行方向後面で発達する。
- 風向が不連続となる位置で風速が極小になっている。
- 低気圧の中心付近は相対的に高温であり、そのピークは低気圧循環のすぐ東側にあり、特に高度700hpaで顕著である。
第58回 気象予報士試験 実技2
- 中層に、8分雲量で2の高積雲がある。
- 雲に対応した領域は湿数3℃以下の地点が多く湿潤で、暖気移流の場である。
- 乾燥した下降流域になっている。
- 地点イは18日目9時までに風が弱く、地点アはそれ以前に北北西の風が吹き出すと予想されるため。
- 風向が南南西から西北西に変化し、海面気圧が急上昇し、気温が急降下したため。
- 中国山地に沿って等温線とほぼ平行な西南西の風が吹き寒気移流は下関より小さい。
- 中国山地に向かう西北西の風が寒気側から吹き温度傾度の小さい下関より寒気移流が大きい。
- 寒冷前線通過直後の海面気圧の上昇がみられない。
- 寒冷前線通過前は上空に向かって時計回り、前線通過後は反時計回りになっている。
第57回 気象予報士試験 実技1
- 明確な気温の逆転層があり前線面はその上端にあたるため。
- 上空に向かい時計回りに変化しておりその変化が特に大きいため。
- 850hpaの温暖前線は名瀬と鹿児島の間に推測され、状態曲線の前線面は850hpaより低いため。
- 上空に向かって西に傾いており、傾きは次第に小さくなっている。
- 気温場の谷のすぐ西側で、温度と湿数の傾度が大きく、その南西側には湿潤域が広がる。
- -15℃以下の寒気が中国東北区から日本海南部に南東進してくる。
- 高気圧は勢力を強めながらゆっくり移動する一方、低気圧は発達しながら、高気圧より速く東北東進し、等圧線の間隔が狭まるため。
第57回 気象予報士試験 実技2
- 雲域Aの西端に正渦度極大点がある。
- 寒冷前線の南東側に平行に伸びている。
- 40〜60ノットの強い南西風の領域で327Kの高相当温位領域に発生している。
- 20ノット程度の南西風で、333Kの高相当温位気塊が流入する領域に発生している。
- 北海道の北の前線に500hpa面のトラフが西方から深まりながら接近するため。
- シアーラインの南東側は南西の風で相対的に強く、北西側は北よりの風で相対的に弱い。
第56回 気象予報士試験 実技1
- 中心の南とその南西にかけて広がっている。
- 地上低気圧の中心は500hPaの強風軸の北側に位置している。
- 朝鮮半島付近の500hpaのトラフが地上の低気圧の北西側から南東進して近づいてくる。
- 強雨域は帯状の南西側ほど、幅が狭くなっている。
- 積乱雲が圏界面まで発達し、その付近で雲が水平に広がるため。
- 地点aの風のほうが北緯32°の風より強く収束が見られる
- 上空に向かって南東から南西に時計回りに変化している。
- 500hPaの風速が大きい。
- 上空に向かって北西から西南西に反時計回りに変化し、2.5kmより上はほぼ西南西の風である。
- 南南東の風が強くなり、急な気温の上昇が止まったため。
- 風が南南東から西に時計回りに変化し、気温が急下降したため。
第56回 気象予報士試験 実技2
- 北西側は雲が少なく、南東側に発達した対流雲があり、上部から吹き出した上層雲が南に広がっている。
- 南東側で相対的に強く、最大40ノットに達するが、北西側は最大15ノットで弱い。
- 寒気がトラフに先行し、トラフの西側に寒気がないため、発達する可能性は低い。
- 850hpa面では等温位集中帯の南縁が風の循環中心をとおり、すぐ西に500hpa面のトラフが迫り温帯低気圧の特徴を備える。
- 数値予報より中心気圧が深まりより発達すると予想している。
- 台風が弱まり本州の南へ進んだ。
- 本州の日本海前線上に低気圧が発生した。
- シアーラインは帯状エコーの東縁にある。
第55回 気象予報士試験 実技1
- 逆転層の下方は概ね北北東の風、上方は概ね南西の風で上層の風のほうが強い。
- シアーラインの西側は風が弱く相対的に低温であり、東側は南寄りの風で相対的に高温である。
- 関東地方に見られるシアーラインは地上付近の寒気層によって北上がさまたげられている温暖前線である。
- 321K以上の暖湿気塊が風速55ノットの南風で侵入し、陸上で25ノットに弱まる。
- 暖湿空気が山地の南斜面に吹き付ける。
- 暖湿空気が温暖前線面に乗り上げる
- 地表付近の気温は氷点下だが、その上空に0℃以上の気層がある。
第55回 気象予報士試験 実技2
- 地上低気圧の中心付近は雲頂高度が低く、中心の東側では雲頂の高い雲が南北に連なっている。
- 暗域は強風軸とほぼ同じ位置にある。
- 暖気移流、寒気移流共に黄海の低気圧より明瞭である。
- 渦状の雲の南側に暗域が流れ込み平島の西側の上中層に乾燥空気が流れ込んでいる。
- 平島のすぐ西に333K以上の高相当温位域が
- 南南西から北北東にのびその西側で等相当温位線が混んでいる。
- 平島付近では南から南南西の風、その西側では南西の風で収束がみられる。
- 温度風が西から東に向いているため。
- 相当温位の極大域にほぼ対応して湿数が小さくなっている。
- 上方に向かって相当温位が小さくなっているため。
- 下層に湿数が小さく相対的に高相当温位の暖湿な東風が予想されている。
第54回 気象予報士試験 実技1
- 日本の南のgwは東に移動している低気圧に伴うものであるため。
- 風向は地衡風と比べ反時計回り方向にずれている。
- 雲域の北側の縁に強風軸が位置している。
- 北東部から南西部にかけて周囲より気圧が高く、下層の気温は周囲より低くなっている。
- 逆転層上端付近の温度はほぼ同じだが850hpaから地上にかけての気温は低下している
- 0℃付近で、雪片が融解しながら落下している。
- 0.9kmの風が東から北東に変わり、1.2kmの風が南から東に変わっている。
第54回 気象予報士試験 実技2
- 台風の進行方向右側で風速がつよくなっており、中心のすぐ東で最も強い80ノットが予測されている。
- 中心部の相当温位がもっとも高い。
- 気圧の尾根付近は850hpa面の温度場の谷になっている。
- 高気圧中心の軸は地上から850hpaにかけて、高温側に傾いている。
- 中心の北西側から北東側、南東側で中心から100〜300km離れて弧状に分布。
- 暖湿空気は太平洋側の南斜面にぶつかって上昇する。
- 暖湿空気は温暖前線のところで収束し上昇する。
第53回 気象予報士試験 実技1
- 低気圧の中心が遠ざかることに伴う気圧上昇量に比べ,寒冷前線の接近による気圧の下降量が大きかったため。
- 雲頂高度が高く,雲域の北縁が明瞭で高気圧性の曲率をもって(バルジ状となって)いる。
- 湿度が低く,上空に向かって気温が高くなっている。
- 降水粒子が,乾燥した層を落下する途中で蒸発するため。
- 関東の南東海上は強い上昇流域だが,低圧部は下降流域または弱い上昇流域である。
- 関東の南東海上は湿数が小さく湿潤だが,低圧部は相対的に湿数が大きく乾燥している。
- 低圧部には,高温の極値がある。
- 山岳の風下の下降流による昇温(フェーン)。
- 山地の南~南西斜面に沿って分布している。
- MSMガイダンスは,MSMのモデル地形の分解能が高いため,実際の山地の南西斜面を中心にきめ細かく予想している。
第53回 気象予報士試験 実技2
- 暗域Pは300hpa面の強風軸のすぐ東側を南北にのびている。
- 暗域Qは500hpa面の細長い正渦度域のすぐ北側を西北西から東南東にのびている。
- どちらの雲域も暗域に接している。
- 地上低気圧はトラフの直下にある。
- 1008hPaの等圧線で囲まれた領域が低気圧中心の南東側に広がり、関東沿岸付近に新たな低気圧が発生しかけている。
- 暗域Qのすぐ南側にのびる500hPa面の細長い正渦度域が九州付近で南下するため。
- 北東の風が山地にぶつかって上昇する場所。
- 北東の風と南寄りの風が収束する場所。
- 発達した積乱雲からの冷気外出流のため。
まとめ
この丸暗記帳は、実際の試験で、解答を素早く記述することができるようになることを目的として掲載しております。
この丸暗記帳を活用する前提としては、過去の実技試験問題を少なくとも2~3周程度は理解して解いているということがベースになっています。
実技試験問題を解いたことがないのに、いきなり、この丸暗記帳を使っても、ほどんど意味はありませんので、そこは十分ご理解を頂いた上でご活用いただければと思います。
実際の実技試験の過去問は以下で解説していますので、内容の理解が不安な方は、こちらもぜひチェックしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます!