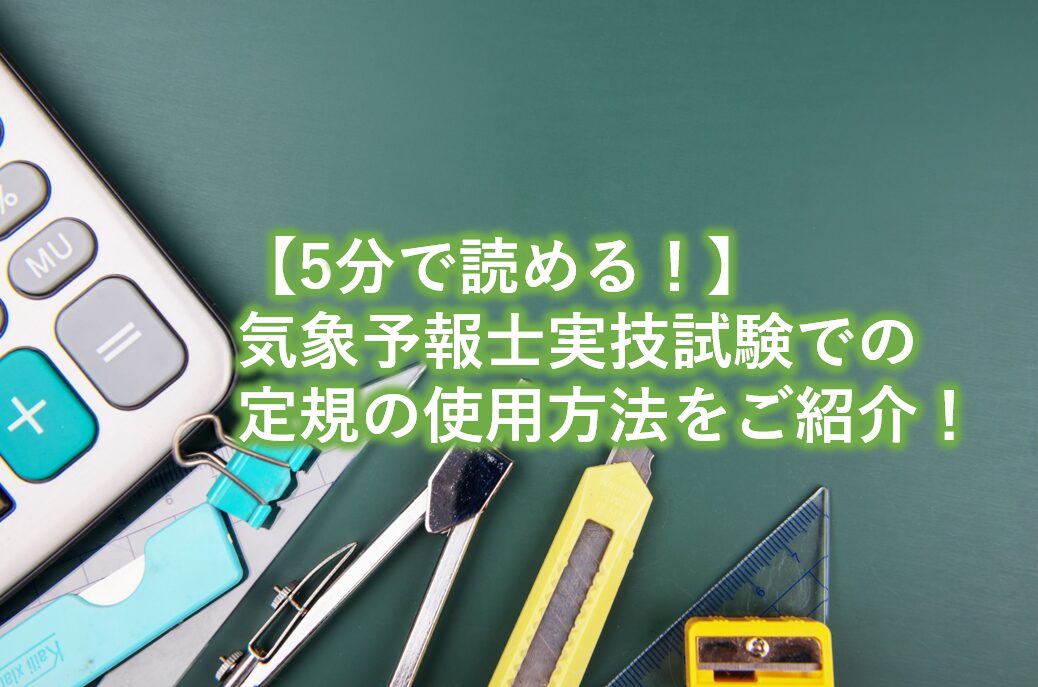皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。
気象予報士の実技試験では定規は必須の持ち物として、明記されています。
当然ですが、試験に使うので記載されているんですね。
皆さんうまく使いこなせていますでしょうか。
定規をうまく使うことによってコンパスがいらなくなったり、短い時間で実技試験問題を解いていくことも可能になります。
使い方に自信のない方や、どんな時に使用するかよくわかっていないよ。という方は是非確認してみてくださいね。
【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!
実技試験で定規はどう使う?
定規とは?
気象予報士試験における定規の使い方を説明する前に、「定規」の定義を確認しておきましょう。
定規というのは直線を引いたり、カットしたりするために用いられるもので目盛があるものもあれば、ないものもあります。
材質はプラスチックが主流で、軽量で扱いやすいのが特徴です。
お気づきの方もおられるかもしれませんが、これと似た道具で「ものさし」というものがあります。
ものさしも定規も一緒でしょ。と思われる方もおられるかもしれませんが違うんですね。
ものさしは物の長さを測るために特化した道具で細長い形状をしていて、材質は木製や金属製が一般的です。
ものを正確に測るためには、温度変化によって伸縮しにくいという特徴を持ち合わせていないといけないため伸縮しにくい木製や金属製が使われています。
では、気象予報士試験ではどちらを使用すればよいのでしょうか。
結論としては、定規で全く問題ありません。
長さを正確に測る必要はありますが、試験で使用するだけですので温度変化もないですし、直線を簡単に引くことができるので。
軽いのもメリットですね。
注意しておいてほしいのは、当然ですが、目盛がついており変形していないもの。
それとプラスチックに色がついておらず、透明で問題用紙まで見えるものがおすすめです。
というのも、トレーシングペーパーを重ねて直線を引く場合、天気図などの緯線、経線に沿って線を引いたり、天気図に含まれる情報を確認しながら線を引くことが多いためです。
個人的にはこのような定規が1つあればよいと思います。
家にあるか確認してみてくださいね。
試験での定規の使い方
ここからは気象予報士試験での定規の使い方をご紹介していきます。
どんな時に使えばよいのか、どの受験回でも必ず必要となる使い方を紹介しますので、ぜひ習得してみてください。
緯度10°の距離
気象予報士実技試験では、緯度10°の距離を測って擾乱の移動距離を出したり、速度を求めたりという問題が毎回出題されます。
ところで皆さん、緯度10°の距離はどのくらいかご存じでしょうか。
気象予報士試験を受験される方であれば知っていて当然かと思いますが、緯度10°は600海里又は1110kmですね。
ノットで速度の答えを出す必要がある場合には前者を、km/hで計算する必要がある場合は後者を使用します。
この速度を求めるときにポイントになるのが緯度10°分の距離です。
経線に正しく定規を沿わせ、数値を読み取るようにしましょう。
写真では北緯30°から40°の距離は22.5mmですが、あせっていると32.5mmなど読み間違えてしまうこともありますので注意が必要です。

低気圧中心間、高気圧中心間、トラフの距離
初期の時刻から12時間、24時間と時間が経過すると、低気圧や高気圧、トラフなどの擾乱は東に移動していきます。
その時間での移動距離を求める問題もよく出題されます。
このとき、緯度10°は場所によって距離が違うので、どこの緯度の距離を使えばよいか迷う方もおられるかもしれませんね。
図の青矢印の距離であれば北緯30°から北緯40°の10°分の距離を使用して移動距離を計算すればよいのですが、黄色矢印であれば北緯40°とはかけ離れた位置にあるため、北緯30°から北緯50°の20°分の距離を定規で計測したあと2で割った平均で緯度10°分の距離を出すのが一般的です。
擾乱の移動と全く関係ない場所の緯度10°分の距離を計測して距離や速度を求めても、正しい数値にはならないので意識しておきましょう。