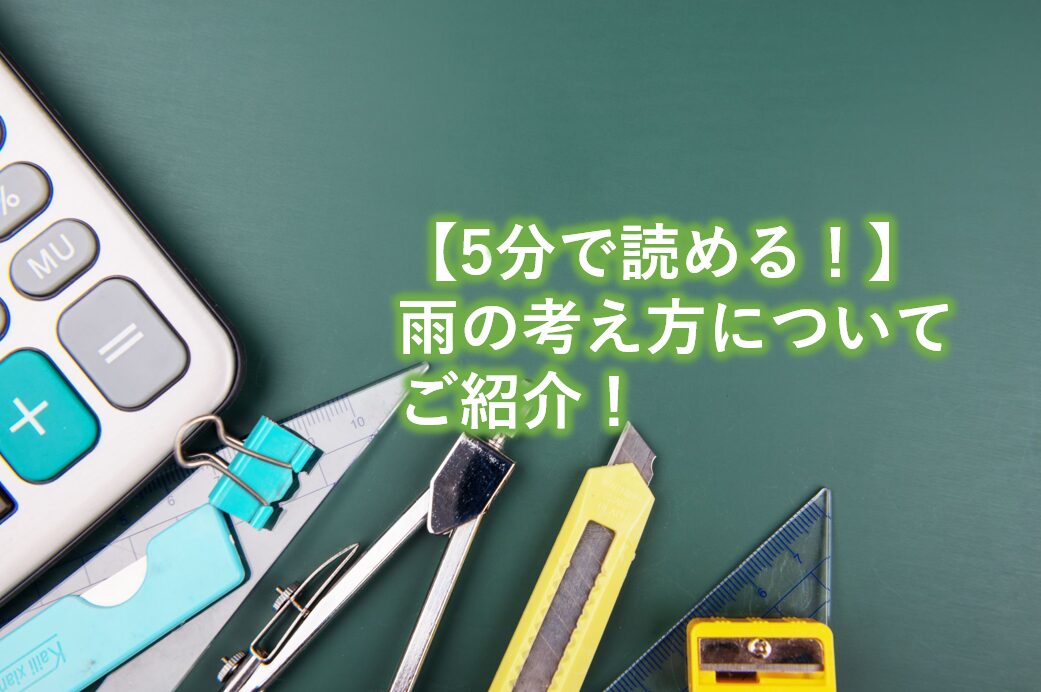皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。
明日、楽しみにしているイベントがあるけど、天気予報では「雨」となっていて気持ちが下がったなんて経験ある方もおられるのではないでしょうか。
どうせなら、やっぱり晴れてほしいものですよね。
ところで、雨ってなんなんだろう。そもそも、なんで空から降ってくるんだろう。
と、真面目に考えたみたことってありますでしょうか。
今回の記事では日常生活に切り離せない雨について考えていきます。
これから先も必ず遭遇するであろう雨を少しでも楽しく感じるために、ぜひ知識を深めていっていただければと思います。
【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!

雨とは何か?
定義は?
まず雨についての定義を確認してみましょう。
雨とは、雲の中の水滴や氷の粒が大きくなって落下し、地表に降る現象のことです。
いわれてみると当然なんですが、ここに重要なポイントが隠されています。
そう、雨は雲がないと、降ってこないんですね。
実は、その雨が降る雲も決まっていて、大別して10種類ある雲のうち、積乱雲と乱層雲と呼ばれる2種類だけ。
どこかで聞いたことある方もおられるかもしれませんね。
では、これらの雲はどうやってできるのでしょうか。
早速、詳しくみていきましょう。
冷たい雨と暖かい雨
雲を考える前に、まず雨の種類を伝えておきます。
雨の種類って何?って思われた方も多いと思いますが、雨には2種類の呼び方があって冷たい雨と暖かい雨というのがあります。
地上に落ちてきた雨の温度が冷たい、暖かいというわけではないんです。
冷たい雨というのは雲の中の温度が0℃を下回る箇所を含む雲から降る雨のことで、0℃より低いということは雲の中に氷晶や氷のつぶなどが含まれている雲になります。
これらが解けて地上に降ってくるものが冷たい雨と呼ばれ、日本などの中緯度や高緯度の地域の雨はほとんどこれにあたります。
一方で暖かい雨というのは雲の中の温度が0℃以上となっており、ここから降る雨が暖かい雨と呼ばれていて、主に赤道に近い気温の高い熱帯地方などで見ることができます。
同じ高度で見ると中高緯度の方が熱帯地方に比べ気温は低くいため、このような違いが生じることになるんですね。
冷たい雨は氷晶や氷の粒が大きくなって、上昇気流に耐えられず落ちながら溶けて水滴となったもの、暖かい雨は水滴が大きくなって、上昇気流に耐えられず落ちてきたもの。
これは、押さえておきたいポイントです。
雨はなぜ降るのか
凝結過程
さてここから、雨を降らせる雲の成り立ちを解説していきます。
まず雲ができるためには、地上にある水蒸気を含む空気が上昇するというプロセスが必要になります。
上昇するためには色々なパターンがあって、地上の空気が温められて上昇する、山に空気がぶつかって上昇する、暖かい空気が冷たい空気とぶつかって上昇するなど。
それぞれのパターンでできた雲から降る雨のことを専門用語で、対流性降水、地形性降水、前線性降水などと言ったりします。
では、上昇した空気がどのように雨になっていくのでしょうか。
それを考える上でまず重要なのが、凝結過程という考え方です。
上空では空気が冷たいので、含むことができる水蒸気の量がきまっていて、空気に含むことのできる水蒸気の量は温度に依存します。
水蒸気を含む空気が上昇していくと、あるところでその空気に含まれる水蒸気量が限界を超え、限界を超えた水蒸気は凝結し、微小な水滴にかわっていきます。
この変化の過程が凝結過程と呼ばれるものになります。
まず、凝結するためには空気中に浮遊するエアロゾルというものを核として水滴の粒である雲粒を形成します。
海塩粒子、巻き上げられた粉塵などの核があると雲粒になりやすいんですね。
雲粒の大きさは半径、約1μm(0.001mm)~100μm(0.1mm)。
雨粒は半径0.1mm~4mmで、半径1mm~2mmの大きさが一番多い雨粒の大きさになります。
普段遭遇する雨もこれくらいの大きさではないでしょうか。
また、雲粒が微小な水滴に成長していく凝結過程では半径の小さなものほど、大きなものに比べ一定時間での成長のスピードが速いことは覚えておいてください。
やかんを沸かした経験を持たれる方も多いと思いますが、目に見えないところが水蒸気、白いところが湯気(雲)です。
空気に入りきらない水蒸気が目に見える形で水滴になったものが湯気(雲)として表れていますので同じ現象であると考えるとわかりやすいかもしれませんね。

併合過程
凝結過程を経てできた雲粒が発達して雨粒になる過程を併合過程と言います。
もともと小さかった雲粒がどんどん成長し大きくなっていくんですね。
この過程がないと、降水にならないため、雨が降るためには必須のプロセスといえます。
冷たい雨では一旦氷晶ができると、それにどんどん水蒸気がくっつこうとして大きくなったり、さらに周りの氷の粒どおしもくっつくことで大きくなります。
これらは昇華凝結過程やライミング、凝集過程と呼ばれるのですが詳しくはこちらの記事で解説します。
【5分で読める!】雪とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!
そして、大きくなった氷晶や氷の粒は一定の速度で落ちてきて溶けて雨となります。
一方、暖かい雨では雲粒が水滴をとりこみながら成長していきます。
窓ガラスに水滴がついていると、落下しながらどんどん水滴を取り込んで大きくなることを想像してもらえればわかりやすいかもしれません。
こうして大きくなった雨粒が地上に落ちてくるというわけです。
また、併合過程では凝結過程とは逆ですが、水滴の半径が大きいほど一定時間での成長のスピードも大きくなります。
大きい水滴の方が小さい水滴に比べ周りの雲粒を取り込みやすいのでこれは、イメージしやすいでしょう。
終端速度
併合過程を経て雨粒が大きくなると地上に落下してきます。
落下してくるときには抵抗が生じるわけですが、その終端速度は、雨粒の半径の大きさに依存します。
具体的には半径0.1mmよりも小さい降水粒子であれば、半径の二乗に比例し、半径0.1mmよりも大きくなると半径の平方根に比例するというものです。
降水粒子が大きくなると、空気抵抗が大きくなりますので終端速度の計算に用いられる抵抗力が異なるため違いが生じることになります。
参考までですが、前者後者の終端速度をV1、V2として数式で表すと
V1=2ρwgr12/(9η)∝r12
ρwは水の密度、gは重力加速度、r1は雲粒の半径、ηは空気の粘性係数。
V2=[(8/3)(ρw/ρα)(g/cd)r2]1/2∝r21/2=√r2
ραは空気の密度、cdは空気の抵抗係数、r2は雨粒の半径。
となります。
式まで覚える必要はないですが、終端速度が降水粒子の半径の二乗または平方根に比例するということは気象予報士試験でも出題されるので、覚えておくようにしましょう。
まとめ
ここまで雨の成り立ちについて紹介してきました。
雨が降るためには雲が必要で、雲ができるためには水蒸気を含む空気が上昇することが必要であることがわかっていただけたかと思います。
日々雨が降っているところもあれば、そうでないところもあるということは、空気が上昇したり下降したりといった現象が地球規模で目まぐるしく起こっていることを意味します。
そう考えると降水現象も面白いですよね。
ちなみに年間の降水量世界一はコロンビアで、日本では沖縄県だそうですよ。
雨が降った時にこのような知見をもって傘をさすだけでも新たな発見が見えてくるかもしれませんね。
【5分で読める!】雪とは何か?仕組み・発生メカニズムを図解でわかりやすく解説!
最後までお読みいただきありがとうございます!