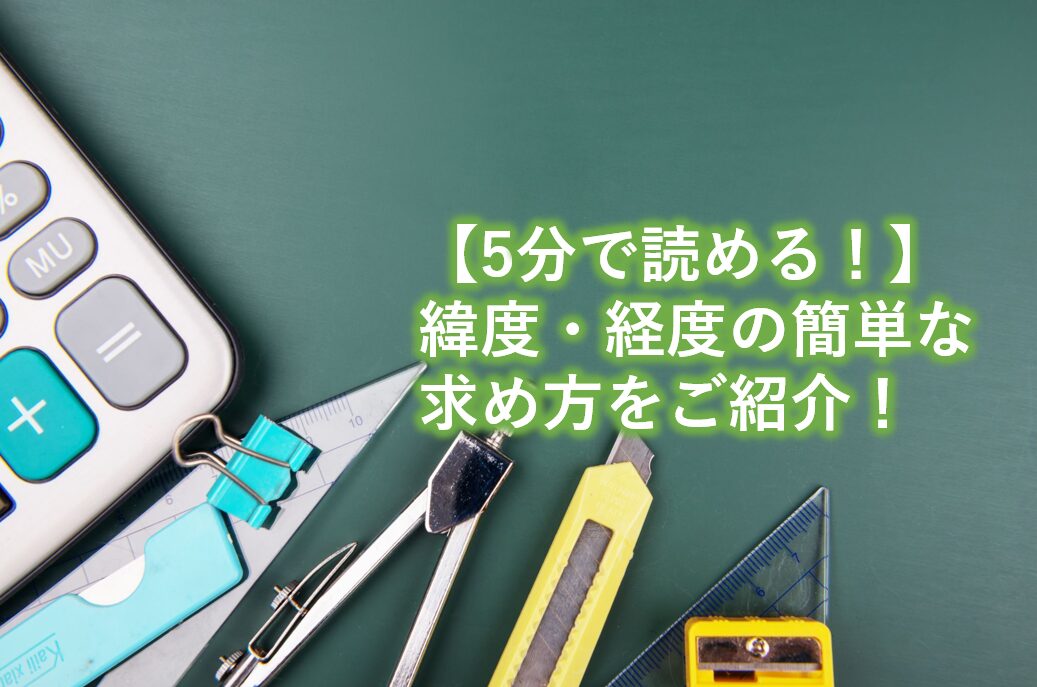皆さんこんにちは!気象予報士のyoshi.です。
実技試験では必ずと言っていいほど出題される緯度・経度の問題ですが、皆さんはどのように問題を解かれているでしょうか。
今回はできるだけ、簡単にそして正確に緯度・経度を導く方法をご紹介します。
実際の試験でも活用できると思うので、ぜひ確認してみてください。
【5分で読める!】千里の道も一歩から。天気や気象がより面白くなる厳選本8選のご紹介!
緯度・経度の求め方のコツ
緯度・経度問題とは?
気象予報士試験では緯度・経度を求める問題がよく出てきます。
例えばこれ、皆さん×での緯度・経度は何だと思いますか?
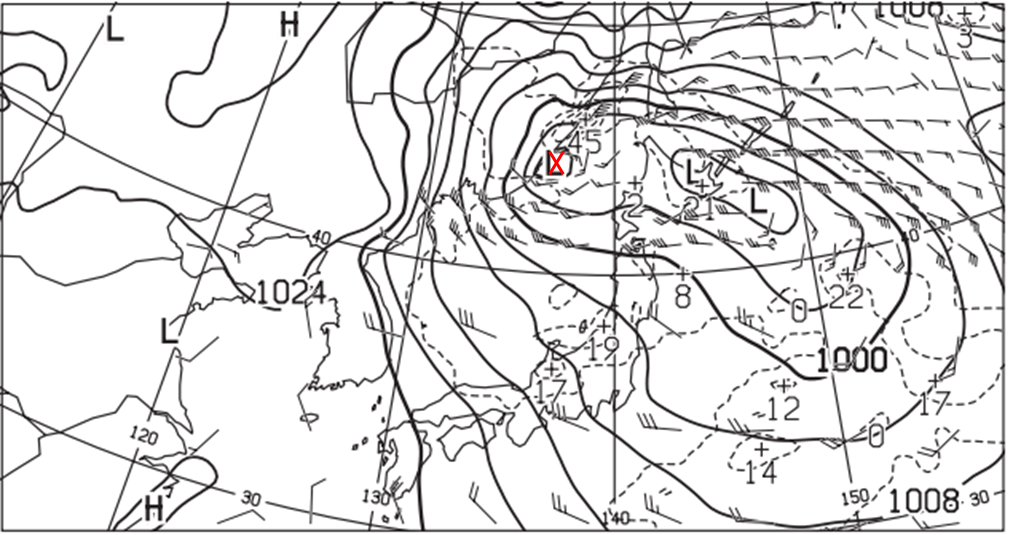
模範解答は北緯44°、東経136°(137°)でした。
わかった方はおめでとうございます。
わからなかった方でも、近いところまでは考えられているのではないでしょうか。
でもドンピシャであてるのって難しいですよね。
緯度・経度は時間をかければわかるけど、結構間違えやすい問題が出題されます。
そして、実技試験は時間がないのですが、このような基礎問題はさっと解きたいし、正解しておきたいのですが、緯度・経度って曲線も含まれるし、ムズイって。。
このように、思われている方も多いのではないでしょうか。
では、その悩みを解決していきますね。
緯度・経度を簡単かつ正確に求める方法
私もこの問題は苦手で目分量や定規をつかったり、コンパスを使ったり、良い方法がないかと模索していました。
でもどれも時間がかかるんですよね。。
どうせ解くなら正解もしたいし。
と、考えてたときに、誰でも簡単かつ短時間でほぼ正確に緯度・経度を出せる方法を発見したんですね。
それを皆さんにもこっそり伝授します。
それがこれです。↓